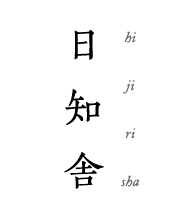「ここはのう、里とは全然生き方が違うとこだ」
月山山麓の北西、鶴岡市田麦俣。大陸からの季節風がとめどない雪に変わる山間の集落。針葉樹や家壁の鈍色が辛うじて顔を出し、雪下ろしのわずかな音が木霊する。江戸時代、湯殿山を目指す人々が宿泊した六十里越街道の要所は、白い静寂の中にあった。

「男勝りみたいに丈夫な婆さんであったのよ」。
壁掛けの写真を見上げ遠藤康明さんがいう。「今の国道と違って山道を、かんじき履いて3、40km背負って、冬のうちに里の方へ出すわけ」。祖父はかんじきを、父は鍬の台を作り、母はそれらをここ田麦俣から約12km離れた落合まで背負った。「雪はどんな時代になっても、雪国には降る」。豪雪地帯に今も必需品のかんじきを、康明さんは山が雪に閉ざされるこの時期、作り継いでいる。

製作は春に始まる。イタヤカエデを採集し、秋まで水に浸して雪をかくツメに。秋には樹齢5年ほどの節のないオオバクロモジを調達し、祖父は囲炉裏で、康明さんは薪ストーブの灰汁で曲げて、輪の部分に加工する。輪にツメを組み合わせる角度と安定性に余人の及ばぬ技が宿る。代々の手先の起用さから、屋号は「からくり儀右ェ門」と呼ばれた。

出羽三山詣でによって発展した集落だが、そのにぎわいが衰えると養蚕や炭焼きが行われるようになった。国が養蚕を進め、遠藤家も夏はこれを営んだ。時代とともに需要と生業は変遷し、集落の人口も移り変わった。康明さん自身、かつて稲作や畜産を手がけたこともあったが、雪深く農業が困難なその土地では「何としても大変であった」。いまは「山のくせ」を利用し、山菜やキノコを採集、山の恵みで生計を立てる。
「この大地はやぁ、いつになってもなくなんないわけ。残っていくわけ。やっぱり、人間は大地がねえと生きていけねえさけや。何としたって。だから大地を大事にしていく生き方しねえとや。やっぱり好きな人、思いのある人が気にかけて、守っていくしかねえと思うなやの」
集落は白く包まれていた。一切を吸い込む静寂の中で、雪だけがとめどなく降りてくる。