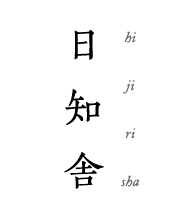毎年7月1日。月山が開かれる。この日を境に山の気配は一変し、山麓に暮らす人々の活力は、遠近から月山を目指す参詣者や登山者を迎える一点へ凝集されていく。こうしてまた夏が始まる。
抜ける青空と輝く緑に、残雪と白衣がくっきりと浮かぶ。月山を象徴する色彩の中を行く道者。時折首に白い紐のようなものが揺れているのを見るだろう。紙縒りを不思議な形に編んでつくられたそれは、注連(しめ)と呼ばれる。
10年近く前に注連を初めて首にかけたとき、誰から何の説明を受けたわけではなかったものの、常ならざる感覚を覚えた。
注連はいったい誰の手でつくられ、どんな意味があるのか。「結界」というぐらいで、詳しくは知らずに過ごしてきた。昨夏、羽黒山山麓で宿坊を営む大江弘子さんを訪ねた。紙縒りで曲線をつくり結び合わせる「淡路」と直線を折り畳む「石畳」という結び方をもとに、それらを組み合わせ首にかけられる円形にすることなど、様々な知見を得たが、やはりその意味は不明なままだった。
今夏、羽黒に隣接する櫛引で、冬に向けて注連を作る遠藤重嗣さんを訪ねて、注連の意味を解決する糸口をようやく見つけた。

黒川能で知られる王祇祭では、当人(当屋の人)や子どもなど、ごくわずかな人だけがご神体である「王祇様」に触れることができる。彼らが共通して身につけるものが注連だ。遠藤さんは、現在それを編むことができるただ1人の伝承者だ。
王祇祭のご神体は、3本の木柱の頭に幾重もの「紙」が巻かれている。「紙」はそこに神が下りてくるしるしである。ご神体の「紙」は、20年に1度「衣替」という行事で新しいものに取り替えられる。
一方、注連は、古い「紙」を紙縒りにし、つなぎ合わされてつくられる。つまり、注連とは神がやどるしるしであり、さらには神の象徴とさえいえるのではないか。
「教えてもらったためしはねんだもの。家のおやじも、1本注連を残しておいたわけだ。これみて覚えれと」
遠藤さんは神職である父が逝去して以来、13年間注連をつくり続けてきた。その手仕事が次代へと受け継がれたのは、1本の注連が残されたからだ。信仰を背景にしたこの土地固有の手仕事は、次の世代へと結ばれることを静かに待っている。