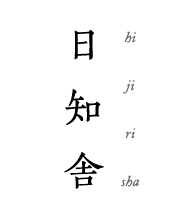とうとうと流れる最上川からその支流鮭川に道をとり、さらに真室川を上る。川沿いに小さな平野が開けてくる。そこに自生する漆を、かつて転々と移動しながら掻いて回った人々がいたという。一度は消えたこの「掻き子」の姿が、今また見え隠れしている。
入梅のころ、漆林で佐藤学さんと再会した。27歳にして漆工暦は10年。普段は「真室川うるしセンター」に勤務し、自宅に「うるし工房 学」を営む。大工の父をもち、材木や鉋屑の木の香りに囲まれて育った。「地元で仕事がしたかった」。高校卒業後、同センターで四年間の漆塗り研修を修了。その後独立し工房を立ち上げ、真室川で唯一の漆掻き栗田政次さん(79)から漆掻きを学んだ。

栗田さんは40代まで農家を営んだが、自身が「本当の漆掻き」と賞す管竹松さんに出逢い漆の世界へ。管さんは各地を回っていたが、「いい人みつかって」真室川の釜渕に定住した。「職人の仕事は身体で覚えるしかない」。栗田さんは常人ならぬ技量をもつ管さんに同行し仕事を覚えた。こうして、かろうじてその仕事はこの地に伝えられることとなる。
生きている漆の木を傷つければ、木は自らを治癒しようと傷口に樹液、すなわち漆を滴らせる。それを採集するのが漆掻きだ。樹液が最も多く分泌される「盛[り」の時期に十分な漆を採るため、少しずつ木を傷つけ、傷つけるのに慣れさせ、漆の採れる木へと「育てていく」。一度掻いた木は漆が出なくなるからその年に倒す。

「その掻き方を「殺し掻き」といって、文字通り殺すんです。でも、一本の木が死んでも根が生きてれば新しい芽が出る。そうやって二代目、三代目と木を増やしていくんです」。
漆を傷つける佐藤さんの丁寧な仕事は、自然と人の関係がどういうものかを直裁に示しているように思えた。
佐藤さんは今、真室川の風土に合った漆工を考えている。塗りに最重要なのは温度と湿度だが、それらは土地に固有のものだから。世代を超えて伝えられる技。技を支える風土。そこに大切なものが見え隠れしている。